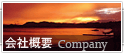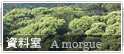□ ホウライカガミ
□ キヨウチクトウ科
□ 生えている場所:西庭
□ 海岸近くの岩場に多いつる植物で、茎は長くのび槙の木とアセローラの木に巻きついている。葉は楕円形で厚く、光沢があります。最近ではオオゴマダラの食草としてよく知られる陽になりました。オオゴマダラが大空を悠々と飛んでいられるのは、幼虫時代にこの毒草を食べ、体内に毒蓄えているためで、野鳥はそのオオゴマダラを食べても吐き出してしまうようです。優雅に飛ぶ日本最大の蝶の秘密はホウライカガミの毒にあったのです
 △ ホウライカガミ
△ ホウライカガミ

△ホウライカガミの種子
 △ ホウライカガミの種子 右側の茶色の種子は熟した物、弾けて風に乗って運ばれる。
△ ホウライカガミの種子 右側の茶色の種子は熟した物、弾けて風に乗って運ばれる。

 △ ホウライカガミ花と種子 ■野石積みの家 ①東庭 ■撮影年月日:2010年6月27日
△ ホウライカガミ花と種子 ■野石積みの家 ①東庭 ■撮影年月日:2010年6月27日 △アカバナチシャノキの花の蜜をすうオオゴマダラ ■撮影場所:野石積みに家 ⑤前庭 ■撮影年月日:2010年6月27日
△アカバナチシャノキの花の蜜をすうオオゴマダラ ■撮影場所:野石積みに家 ⑤前庭 ■撮影年月日:2010年6月27日





 △ブッソウゲ(アカバナ)の葉にオオゴマダラ ■撮影場所:野石積みの家 ⑤前庭 ■撮影年月日:2010年6月27日
△ブッソウゲ(アカバナ)の葉にオオゴマダラ ■撮影場所:野石積みの家 ⑤前庭 ■撮影年月日:2010年6月27日
□ 翅をひろげると15㎝にもたっする。日本産のチョウでは最も大きなチョウである。この大きな翅うぃいちぱいにひろげ、ゆったりと飛ぶ姿は優雅そのものである。とりわけ大きな黒い縞に入った白い翅の模様はよく目立ち、チョウにまったくなじみのない人にでも、まさに熱帯にきた感じを与える。土地の子供たちは「シンブンチョ」と呼んで親しんでいる。
▽オオゴマダラの乱舞 ■撮影場所:摩文仁の丘(県平和祈念公園) ■撮影年月日:2010年6月23日





 △オオゴマダラ ■撮影場所:摩文仁の丘(県平和祈念公園) ■撮影年月日:2010年6月23日
△オオゴマダラ ■撮影場所:摩文仁の丘(県平和祈念公園) ■撮影年月日:2010年6月23日
■ マダラチョウ科。沖縄本島以南の熱帯アジアに分布する。羽を広げると15㎝から20㎝にも達する国内最大のマダラちょう。幼虫はホウライカガミ(キョウチクトウ科)を食草にしている。

△写真左よりホウライカガミの落ち葉(黄色になって落ちる)長さ12㎝幅7.7㎝、中は生葉の裏側、右側は生葉の表 2010年3月5日採取